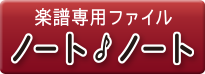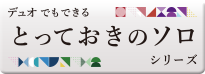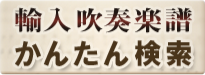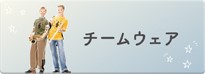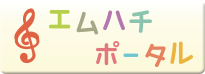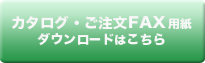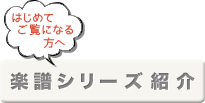サンプルPDF
- シリーズ
- MUCS 輸入吹奏楽クラシック作品(フルスコアのみ)
- 解説
- Carl Fischer Music
957年、アーノルドが、イギリスのBBC放送が主催したライト・ミュージック・フェスティヴァルのために作曲した曲です。原曲は管弦楽曲で、のちにアーノルド自身が吹奏楽に編曲、イギリスのノヴェロから出版していますが、アメリカのノースウェスタン大学のバンド・ディレクターだったジョン・ペインター(1928~1996)が編曲、1978年にカール・フィッシャーから出版された楽譜も演奏されています。
それぞれの楽章について、アーノルドは次のように述べています。
●第1楽章 ペザンテ(重々しく)Pesante
この舞曲はゆっくりとしたストラス・スペイ(スコットランドの舞曲の名で、4/4拍子でやや激しく、変化に富む曲)のスタイルをもち、「スコッチ・スナップ」と呼ばれる反転した付点音符が多く用いられる。このストラス・スペイという舞曲の名は、スコットランドのスペイ(スコットランド北部のグランビアン山脈のなかにある谷)から起こったものである。
●第2楽章 ヴィヴァーチェ(速く、活発に)Vivace
この舞曲は活発なリール(4/4拍子の舞曲で、スカンジナヴィアからスコットランドに移入された元気で速い曲)で、変ホ長調ではじめられ、同じ旋律が繰り返されるたびに半音ずつあがっていき、バスーンで奏せられるト調まで繰り返される。最後の舞曲で再びもとの変ホ長調に戻る。
●第3楽章 アレグレット(快速に)Allegretto
この舞曲はヘブリデーズ諸島(スコットランド北西部の島)の歌のスタイルをもち、この島々の夏の日の海や山の印象を表現したものである。
●第4楽章 コン・ブリオ(輝かしさをもって)Con brio
この楽章はヴァイオリンの解放弦によるアルペジオ(吹奏楽編曲ではサクソフォーンが受け持っている)を多く用いた、活発なフィーリングをもつ曲である。
以上の解説のように、第1楽章はゴツゴツしたリズムとバグパイプのような響きをもち、第2楽章では同じ旋律が半音ずつ上昇しながら繰り返され、第3楽章ではオーボー、バスーン、それにトランペットのソロなどがきかれます。ハープやチェレスタも加えられ、スコットランドの色彩豊かな舞曲による組曲です。
(秋山紀夫) - 編曲者
- ジョン・ペインター (John Paynter)
- 作曲者
- マルコム・アーノルド (Malcolm Arnold)
- 編成
- Piccolo I
Piccolo II
Flute I
Flute II
Oboe I
Oboe II
English Horn
Clarinet I
Clarinet II
Clarinet III
Alto Clarinet (in Eb)
Bass Clarinet
Contrabass Clarinet (in Eb)
Bassoon I
Bassoon II
Contra Bassoon
Alto Saxophone I
Alto Saxophone II
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone
Cornet I
Cornet II
Cornet III
Trumpet I
Trumpet II
Horn I
Horn II
Horn III
Horn IV
Tenor I
Tenor II
Tenor III
Baritone (Treble Clef)
Baritone (Bass Clef)
Tuba
String Bass
Harp
Timpani
Percussion