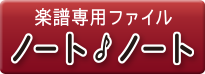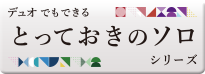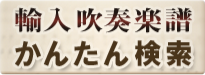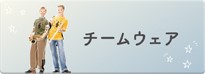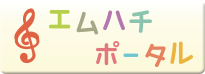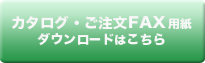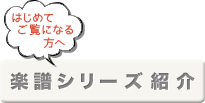No.49 息を聴け
「息を聴け」……それは、その行動はもとより、そうすることで得られる“音の存在”“まわりの空気”“音楽の流れ”などをみんなで共有したいと想い描いた、私たちの「願い」そのものでした。
今回新潮社から出版された『息を聴け』、この物語は、視覚障害者である彼らと私が、ふとしたきっかけで出会い、音楽に向き合ってゆく姿を、ありのまま描いたものです。
話の序盤、「見えない壁」が私たちを取り囲み、音楽のスタート台にすら立てない日々が続きます。それは、彼らの持つ障害が……というだけではなく、ごく単純に、人間の持つ弱さであったり、立ち向かう勇気であったりと、生きてゆくために必要なエナジーを身につけるための「大切な壁」であって、決して難攻不落の壁ではありませんでした。
障害が有る無しに関わらず、人が生きてゆく過程には、必ずといってよいほど、何層もの「壁」が立ち塞がります。しかし、その壁の存在をしっかりと認識したうえで、再び辺りを見渡してみると、驚くほど風景が変わっていることに気づかされます。壁は、壁ではない、と。
音楽とて例外ではなく、やはり、そのさまざまな「壁」に何度も遭遇します。私自身も中学生時分、初めて手渡されたDrs.の楽譜を見て「こんなのできるわけがないや」と、挑戦する前から諦めてしまうという、なんとも恥ずかしい経験をしたことがあります。
結局、どうやってその譜面を演奏したのか。今となっては全く思い出せませんが、当時の顧問の先生に「やってみなきゃわからないぞ」と口酸っぱく言われた記憶だけが、鮮明に残っております。
その「やってみなければわからない」世界のなかで待ち構えている、いくつもの「壁」。私たちが楽曲を演奏するうえで、絶対避けては通れないポイントに必ず用意されています。たとえば、楽譜が複雑で読めない、リズムがわからない、ピッチが取れない、うまく歌えない……などと、やればやるほど、いろいろな音楽に出会えば出会うほど、その壁の数は増えてゆき、演奏者の頭を悩ませます。
が、しかし、それら「壁」の存在以上に、「かっこよく吹きたい!」「いい音楽をやりたい!」という、漠然ながらも、もっと大きな「希望」が、演奏者にはあるはずです。その「希望」さえ見失わなければ、きっと、壁が壁でなくなる瞬間が訪れますし、ほんとうの、本物の「音楽」にきっと出会える瞬間がやってきます。
その瞬間に立ち会えることこそ、音楽のほんとうの喜びだと、私は心から信じています。
出会わなければわからない、立ち向かわなくてはわからない、そんな人生をくれた音楽に感謝するとともに、これから出会うであろう、まだ見ぬ音楽や仲間に、私は心底ワクワクしております。この『息を聴け』で描いた世界は、まさにその「ワクワク感」によって突き動かされた私が、まるで少年のように彼らと音楽を追い掛け続けた「冒険記」。
この冒険の未来に、いったい何があるのか。その答えを探す旅は、まだ始まったばかりです。
今回新潮社から出版された『息を聴け』、この物語は、視覚障害者である彼らと私が、ふとしたきっかけで出会い、音楽に向き合ってゆく姿を、ありのまま描いたものです。
話の序盤、「見えない壁」が私たちを取り囲み、音楽のスタート台にすら立てない日々が続きます。それは、彼らの持つ障害が……というだけではなく、ごく単純に、人間の持つ弱さであったり、立ち向かう勇気であったりと、生きてゆくために必要なエナジーを身につけるための「大切な壁」であって、決して難攻不落の壁ではありませんでした。
障害が有る無しに関わらず、人が生きてゆく過程には、必ずといってよいほど、何層もの「壁」が立ち塞がります。しかし、その壁の存在をしっかりと認識したうえで、再び辺りを見渡してみると、驚くほど風景が変わっていることに気づかされます。壁は、壁ではない、と。
音楽とて例外ではなく、やはり、そのさまざまな「壁」に何度も遭遇します。私自身も中学生時分、初めて手渡されたDrs.の楽譜を見て「こんなのできるわけがないや」と、挑戦する前から諦めてしまうという、なんとも恥ずかしい経験をしたことがあります。
結局、どうやってその譜面を演奏したのか。今となっては全く思い出せませんが、当時の顧問の先生に「やってみなきゃわからないぞ」と口酸っぱく言われた記憶だけが、鮮明に残っております。
その「やってみなければわからない」世界のなかで待ち構えている、いくつもの「壁」。私たちが楽曲を演奏するうえで、絶対避けては通れないポイントに必ず用意されています。たとえば、楽譜が複雑で読めない、リズムがわからない、ピッチが取れない、うまく歌えない……などと、やればやるほど、いろいろな音楽に出会えば出会うほど、その壁の数は増えてゆき、演奏者の頭を悩ませます。
が、しかし、それら「壁」の存在以上に、「かっこよく吹きたい!」「いい音楽をやりたい!」という、漠然ながらも、もっと大きな「希望」が、演奏者にはあるはずです。その「希望」さえ見失わなければ、きっと、壁が壁でなくなる瞬間が訪れますし、ほんとうの、本物の「音楽」にきっと出会える瞬間がやってきます。
その瞬間に立ち会えることこそ、音楽のほんとうの喜びだと、私は心から信じています。
出会わなければわからない、立ち向かわなくてはわからない、そんな人生をくれた音楽に感謝するとともに、これから出会うであろう、まだ見ぬ音楽や仲間に、私は心底ワクワクしております。この『息を聴け』で描いた世界は、まさにその「ワクワク感」によって突き動かされた私が、まるで少年のように彼らと音楽を追い掛け続けた「冒険記」。
この冒険の未来に、いったい何があるのか。その答えを探す旅は、まだ始まったばかりです。
熊本県・熊本県立盲学校アンサンブル部
冨田 篤
団員数:男子3名 女子6名 ※団員数は掲載当時のものです。
モットー:明るく・強く・精いっぱい
※冨田篤氏がトレーナーを務める熊本県立盲学校アンサンブル部は、2005年、 第28回全日本アンサンブルコンテスト大学の部で金賞を受賞しました。
冨田篤 著
書籍「息を聴け」 〜熊本盲学校アンサンブルの挑戦〜